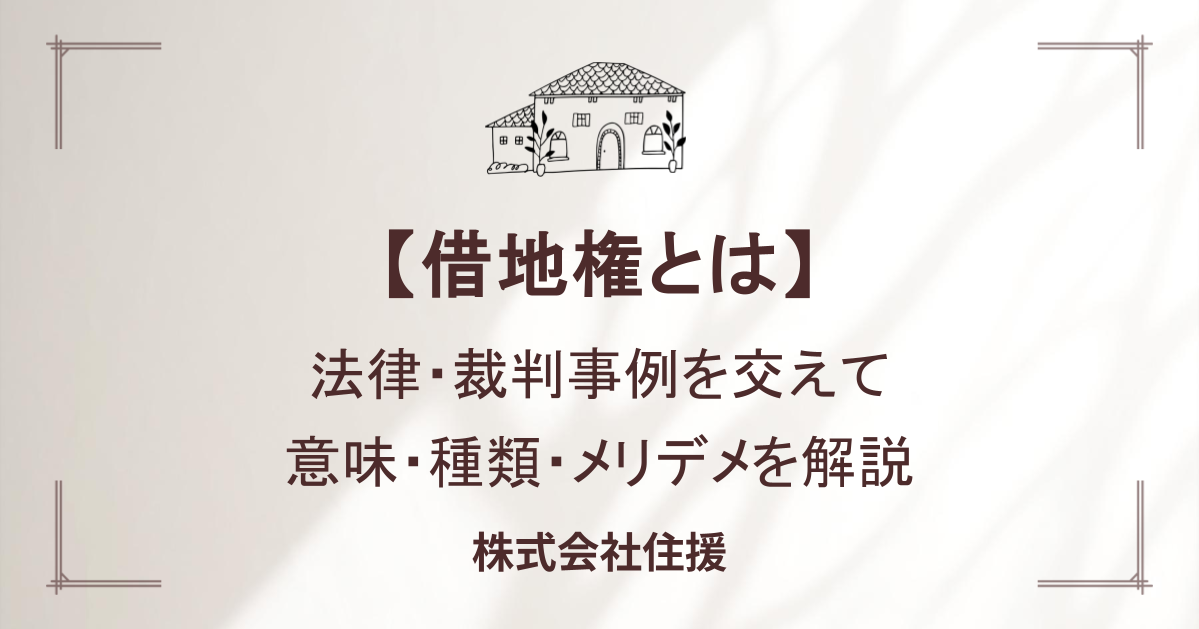監修者
住援株式会社 代表取締役社長
辻 祥平 | Tuji Shohei
多くの不動産業者が「顧客を騙して稼ぐ」ことが一般的な中、自分の周りの大切な人々に良い不動産を提供したいという想いで創業。「不動産業界の真実を本音で伝える営業スタイル」「綿密な収集シミュレーションの提供」「お客様が真に納得するまで取引を進めないという信念」に基づき行う提案からお客様からの絶大な信頼を得る。実績:賃貸・売買 総合売上高1位 / 執行役員 (前職不動産会社)
本記事のポイント
借地権とは何か?
他人の土地を借りて、その土地に自分の建物を所有する権利です。土地は借り物(地主の所有)で建物だけ自分の所有となるため、「土地は他人、建物は自分」という性質があります。法的には「建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権」と定義され(借地借家法)、土地に建物がない資材置き場や駐車場などは借地権に含まれません。
借地権の主な種類は?
大きく分けて「旧法借地権(旧借地法)」と「新法借地権(借地借家法)」があり、さらに新法には普通借地権と定期借地権(一般定期・事業用・建物譲渡特約付き等)が存在します。また、土地に対する物権である地上権も建物所有を目的とすれば借地権と同じ扱いです。
借地権の契約期間と更新方法は?
旧法借地権は契約書で定めた期間(鉄筋コンクリートなど堅固建物なら60年以上、その他なら30年以上など)で開始し、以後は堅固建物30年、非堅固20年で更新されます。新法の普通借地権は初回30年以上、更新時は最初20年、以降10年ごとが原則(更新料・承諾料を払えば更に延長可能)。定期借地権(一般・事業用・建物譲渡)は更新なしで期間満了時に土地を返還します。
費用は何がかかる?
毎月の地代は土地価格や用途で変動し、普通借地権なら更地価格の1%前後(住宅地で固定資産税額の3~5倍程度/年)程度が相場です。更新料・承諾料は相場が明確に決まっているわけではありませんが、更新料は更地価格の3~5%前後、承諾料(譲渡・建替え等)は借地権価格の5~10%程度が目安です。また、保証金や敷金、土地境界確定測量、登記費用(登記免許税0.2~0.4%程度)などの初期費用も必要です。
借地権のメリット・デメリットは?
メリットには「土地の固定資産税が不要」「所有権付に比べ購入費用が抑えられる」「好立地物件で高利回りになりやすい」といった点があります。一方デメリットは「融資を組みにくい」「売買流通性が低い」「地代や更新料増加リスク」「建て替え等の際は地主承諾が必要」などです。借地権は土地そのものを所有しないため、土地部分は借地人の資産になりません。
借地権は相続可能?
借地権は相続財産であり、法定相続人が相続します。特別な地主の許可は不要で、通常は借地上の建物の名義を相続人に変更(相続登記)し、地主に通知しておけば足ります。借地権自体に登記がある場合は相続人名義への登記移転も行います。兄弟で共有相続するとトラブルになりやすいので避け、遺言で承継者を決めておくのも一案です。
借地権の売却は可能?買取請求権は存在する?
借地権付き建物は第三者に売却可能ですが、賃借権の場合は通常、地主の承諾が必要です。承諾料は借地権価格の1割程度が相場です。旧法借地権では契約終了時にテナントが「建物買取請求権」を行使でき、地主に建物の時価での買取りを求められます。底地(借地権が設定された土地のこと)は地主所有の土地部分を指します。借地権と底地権を両方取得すれば建物付き土地として売却しやすくなります。
借地権に関するトラブルや判例は?
地代改定請求では、借地借家法が強行法規であるため、賃料に関する特約があっても法定の増減額請求権が妨げられることはないと最高裁が判断しています。更新拒絶では地主の権利は限定的で、契約満了時に「遅滞なく異議」を述べる必要があります。正当事由がない場合は裁判で拒絶が否認されることもあります。最近はデジタル化対応で契約書類の押印不要化などの改正がありましたが、借地権の基本ルール自体は大きく変わっていません。
借地権の基本知識
借地権の定義・概要
借地権は「他人の土地を借りてその上に建物を建てる権利」です。建物を所有するための地上権または土地賃借権であり、地主に地代を支払って土地を借りる契約関係です。土地そのものは借地人の資産にはならず、借地権のみが財産です。借地権では建物の所有権は借地人にあり、借地人は建物上の収益を得ますが、土地部分は地主が管理し、建物の建築・増改築などは地主の承諾が必要です。
借地権と地上権の違い
借地権は賃借権(借家法の借地借家法上の権利)ですが、地上権は物権であり登記ができます。地上権も建物所有を目的とすれば借地権と同様に扱われます。地上権は物権なので、原則として地主の同意なく第三者に譲渡・転貸できますが、借地権(賃借権)は賃貸人(地主)の承諾が必要になる点が異なります。
適用法令概要(旧借地法 vs. 借地借家法)
1992年(平成4年)に旧借地法が改正され、以後「借地借家法」で賃借権が規律されています。改正前の旧法借地権では自動更新規定が強く借地人の権利が非常に強く、「一度貸した土地が戻らない」と言われます。一方、改正後の新法(借地借家法)では普通借地権と定期借地権が分かれ、普通借地権でも更新料などのルールが明確化されました。旧法契約は引き続き「旧法借地権」として法律上保護されますが、新たな契約は借地借家法に従います。
借地権の種類と特徴
旧法借地権(借地法)の概要
旧法適用の借地権は、一度地主と契約すれば借地人が更新を求めれば半永久的に更新される権利がありました。建築目的ごとに最低契約期間が定められており、堅固建物なら30年(初回は60年以上)以上、非堅固建物なら20年(初回は30年以上)以上を契約期間とします。更新時も堅固建物30年、非堅固20年が最低期間です。旧法には「正当事由なしに更新拒絶不可」という強い借地人保護があり、地主が更新を拒むには裁判で正当理由を証明しなければなりません。旧法借地権は契約満了後でも更地返還か建物買い取り(借地権者が拒めば立退料なし)が可能です。
普通借地権(新法)の特徴
新法の普通借地権は、最低契約期間30年以上(当初契約・更新とも)と決まっており、契約期間満了時には自動更新されます。更新時には更新料や地代の見直しが生じることが一般的で、法律では最初の更新で20年、その後は10年ずつと定められています。ただし契約でより長期を取り決めることも可能です。普通借地権は旧法と異なり地主の立場が強化され、更新拒絶の正当事由が法律で明確化されています(用途変更や自己利用の必要など)。
定期借地権の分類
| 分類 | 特徴 |
|---|---|
| 一般定期借地権 | 契約期間は50年以上(当初契約)、更新なし。満了時は更地で返還。更新拒絶の正当事由要件なし。 |
| 事業用定期借地権 | 契約期間は10~50年で設定(事業利用目的)、更新なし。満了時に返還。建築制限あり(非住宅用途向け)。 |
| 建物譲渡特約付借地権 | 契約期間30年以上。契約満了時に借地上の建物を地主へ譲渡(売却)して土地を返還する特約付きの借地権。一般定期借地権と比べ普通借地権に近く、借地人の権利が強い。契約満了後は更地返還せずに建物だけ地主が取得します。 |
| 一時使用借地権 | 契約期間が数年以内の超短期借地(例:駐車場や工事用地)で、更新なしの例外的な借地権です。 |
地上権(物権)としての借地権
地上権は物権であり、土地に本来ある借地権と同様に建物所有を目的とする地上権も借地権と呼ばれます。地上権設定時には登記が必要で、借地権(賃借権)と同じく地主に地代を払いますが、物権なので対抗力が強く、第三者への対抗要件も備えています。売買・相続手続きも借地権同様ですが、原則は地主の許諾なく譲渡でき、借地権に比べ利用の自由度が高い点が特徴です。
契約のポイント
契約期間の目安と更新要件
借地契約では、土地利用目的と建物構造に応じた期間を定めます。旧法借地権は堅固建物(例:鉄筋コンクリート造)で60年以上、その他で30年以上が一般的です。新法普通借地権は30年以上、一般定期は50年以上、事業用は10~50年が目安です。更新の要件として、新法普通借地権では更新料や地代見直しが発生し得る条項を契約に盛り込む例が多く、また更新拒絶には正当事由が必要です。更新拒絶を行うには契約満了時に「遅滞なく地主が異議を述べる」手続きが必要です。
更新の流れと更新料・承諾料の相場
契約満了前に借地人から更新の申請があると、地主は契約更新に応じるか拒絶するかを判断します。承諾する場合、通常は更新料の支払いが発生します。更新料相場は更地価格の3~5%程度(または借地権価格の5%前後)とされています。地主の承諾を得て契約を更新すれば、地代改定後の新条件で契約を続行します。拒絶する場合、地主は借地人に退去を求め、必要に応じて立退料を支払います。
契約解除・中途解約の要件
借地契約は法律的に強く保護されており、原則として中途解約は困難です。やむを得ない場合でも、借地法や借地借家法で定められた正当事由がなければ地主から解約を申し入れられません。借地人側は地主の同意がない限り契約途中での解約や撤去も認められにくく、一般的には更新拒絶・期限満了をもって契約を終わらせます。
登記方法と第三者対抗要件
借地権は登録しなくても成立しますが、第三者に対抗するには登記が必要です。借地契約書に地上権登記または賃借権登記を設定すれば、以後の土地売買などで借地権を主張できます。相続で借地権を承継する場合、借地権自体の登記は必須ではありませんが、建物の相続登記(名義変更)をしておくことで借地権の存在を主張しやすくなります。登記には登録免許税がかかり、建物は評価額×0.4%、借地権は×0.2%となります。
費用・コストの相場
地代(月額)の相場
地代は地域や用途、土地評価額により大きく異なります。住宅地では更地価格の0.5~1%/年(固定資産税額の3~5倍/年に相当)程度、商業地ではそれ以上になることがあります。例えば土地価格1,000万円なら年額5~10万円(月額約4~8千円)程度が目安となりますが、利便性の高い場所は相場を上回る場合もあります。
更新料・承諾料の相場
更新料は賃貸借契約更新時に支払う謝礼金で、更地価格の3~5%が目安とされます。承諾料(譲渡承諾料・建替え承諾料等)は契約条項により都度決められますが、一般的に借地権価格の10%程度や、更地価格の3~5%程度が相場です。たとえば、借地権価格1,000万円なら承諾料約100万円、建替え承諾料が更地の3%なら地価1,000万円当たり30万円前後を想定します。
保証金・敷金など初期費用
新規契約時には保証金(敷金)を設定する場合が多く、通常は年間地代の半年~2年分程度です。契約時の印紙代や登記費用(登録免許税0.2~0.4%)も必要です。地境界確定の測量費用(50~80万円前後)や公図・権利証調査、各種登記書類の取得費用も含めると、一般の物件購入に比べて多少手続き費用が増えます。
確定測量・書類作成費用
土地の境界を明確にする確定測量は、借地権を含め不動産売買では重要です。測量会社に依頼すると一般に40~80万円程度かかります。契約書や借地契約書の作成・チェックには司法書士・弁護士の報酬が必要で、各20~50万円程度が相場です。登記にかかる書類取得費用(戸籍謄本、住民票、印鑑証明など)も1件あたり数百~千円、専門家報酬は数万円~数十万円が見込まれます。
メリット・デメリット
借地権のメリット
| メリット | 詳細 |
|---|---|
| 固定資産税不要 | 借地の場合、土地部分の固定資産税・都市計画税は地主負担のため、借地人は土地税の支払い義務がありません。これによりランニングコストが軽減されます。 |
| 初期費用を抑えられる | 土地購入代が不要なため、所有権付と比べ取得費用が低く抑えられます。特に好立地・高額地では借地の物件価格が割安であり、高利回り物件を狙いやすいという投資メリットがあります。 |
| 高利回り物件が多い | 借地権付き物件は土地代がかからない分、賃貸収益率が高くなりやすいです。また、通常は利便性の良い都心近郊地に借地権付き家屋が多いため、資産価値も高くなる傾向があります。 |
借地権のデメリット
| デメリット | 詳細 |
|---|---|
| 融資難易度が高い | 借地権物件は土地を担保にできないため、金融機関の融資審査が厳しくなりがちです。融資を受けても金利は所有権物件より高くなる傾向があり、頭金を多く求められる場合があります(実際、底地・借地物件の住宅ローン金利は1.8~3.5%台が一般的)。 |
| 流動性が低い | 一般市場には借地権付き物件を欲しがる買い手が少ないため、売りに出しても買い手が付きにくい傾向があります。そのため所有期間が長期化しやすく、早期売却が難しい資産です。 |
| 地代・更新料上昇リスク | 契約更新時や地価上昇時に地代値上げが起こることがあります。最高裁も「地代増減請求権は強行規定」であると判示しており、地価や経済指数の変動に応じ借地人から地代改定請求が可能です。借地人としては、将来の地代・更新料負担が増えるリスクを負うことになります。 |
| 建替え・増改築に地主承諾が必要 | 借地契約では建物新築や建替え、用途変更に際して地主の書面承諾が必要です。承諾なしに工事を進めると契約違反となり、場合によっては立退き要求されることがあります。承諾料が必要になるケースも多く、設計や施工計画は地主と十分協議する必要があります。 |
売却・買取請求権
借地権付き建物の売却手順と注意点
借地上の建物は売却可能ですが、所有権付物件と異なる点に注意が必要です。まず、地主への承諾取得が不可欠です(借地借家法により賃借人の譲渡には地主の許可が必要)。一般的に借地権譲渡の際には借地権価格の1割前後を承諾料として支払います。地主の了承を得たうえで買手と売買契約を締結し、その後、法務局で借地権譲渡の登記手続きを行います。売却では契約内容(契約種別、地代、期間、更新料条項等)を買主に開示し、引渡し時には前貸借契約の解除・新規契約の締結手続きも必要になります。地上権設定の場合は地主承諾不要で売却できますが、地上権登記をしていない賃借権では必ず承諾を取りましょう。
底地・底地権とは何か
底地(底地権)とは、借地権が設定された土地そのもののことです。借地権者(借主)側が借りている土地で、借地権付き建物に対する土地の所有権は地主が保持します。つまり地主は土地の「底地権」を持ち、借地人は建物に対する「借地権」を持っている関係になります。底地権と借地権が両方そろうと表題通りの完全所有となりますが、どちらか一方だけでは自由利用が制限されます。売却では借地権と底地権をセットにすれば建物付き土地として売り出せますが、地主が底地権を手放さない場合は借地権のみの売却となり、買主の利用価値が低下します。
旧法借地権における買取請求権の要件
旧法借地権では、借地契約満了時(借地人が更新を請求しないか、地主が正当事由で更新拒絶した場合)に借地人側に「建物買取請求権」が認められています。これは「形成権」として、借地権者(建物所有者)が地主に対し建物の時価(建物の価額+土地の場所的利益)で買い取らせる権利です。要件として、借地権契約が旧法適用であること、契約満了(更新しない)であること、借地人が請求の意思表示をすることなどがあります。行使すれば、地主と売買契約を締結したのと同等の法的効果が生じます。逆に新法定期借地権では建物買取請求権はありません。
相続・譲渡
相続手続きの流れと必要書類
借地権付き建物を相続する場合、基本的な手順は通常の相続手続と同様です。まず、不動産の全部事項証明書などで対象物件を確認し、地主に相続の発生を通知します。次に、相続人間で借地権を誰が継承するか決め、遺産分割協議書や遺言書を作成します。建物の名義変更(相続登記)申請を法務局に行い、必要書類(被相続人・相続人の戸籍謄本、住民票・除票、遺産分割協議書または遺言書、印鑑証明、固定資産税評価証明書など)を添付します。借地権自体は法定相続人に自動承継されるため、通常は借地権の名義変更登記は不要ですが、登記がなされている場合は借地権の移転登記(賃借権移転登記)も申請します。
相続対策としてのポイント
借地権相続では共有を避け、特定の相続人へ単独譲渡するのが望ましいです。共有で相続すると共有者全員の同意が必要となり、売却や建替えでトラブルの元になります。また、相続人以外への遺贈をする場合は地主の承諾が必要です(法定相続は承諾不要)。地主からは相続を機に地代値上げや更新料請求を打診されるケースもありますが、法的には拒否可能です。ただし小額であれば争いを避けるために一時的に応じる判断もあります。相続前に遺言で借地権の承継者を決めておく、固定資産評価額に注意した節税対策(借地権割合を活用)なども検討します。
遺言や承継承諾料の考え方
借地権を遺贈する場合、遺言で承継者を指定しておけば手続きがスムーズです。承継承諾料(承継者が地主に支払う承諾費用)は法律上定められておらず、契約で特約がなければ本来不要です。しかし実務上、地主から「承認料」や「名義変更手数料」の名目で請求されることがあります。法的には、相続による名義変更に対して地主は承諾料を請求できません。地主承諾が要るケース(契約に定めあり)は契約条項に従う必要がありますが、可能なら交渉して低減させるのが得策です。
登記移転の方法
借地権の相続・譲渡登記は、対象物件の評価額に応じて登録免許税が課税されます。建物所有権移転登記は評価額×0.4%、借地権(賃借権)移転登記は同×0.2%です。登記申請は相続人または譲受人が司法書士等に依頼して行うのが一般的で、必要書類の収集と法務局への提出で完了します。借地権登記がされている場合は、登録簿に新所有者として相続人・譲受人名義で登録します。
利用・購入手続き
購入前の事前調査(確定測量・権利調査)
借地権物件を購入検討する際は、土地の境界確定(確定測量)を必ず行いましょう。境界杭・標などが不明瞭な場合は隣地とトラブルになる可能性があり、土地売買時には境界確定が重要です。また、既存の借地契約書を入手して契約内容(契約種別、期間、地代額、更新料条項、承諾料規定など)を詳細に確認します。契約が旧法か新法か、定期か普通かで買主の権利強度が大きく変わります。権利関係の不備(未登記や名義人不明など)がないか登記事項証明書で調査し、隣地所有者との境界や利用規制、地目・用途地域なども確認します。専門家(不動産業者や司法書士)に依頼して権利調査・測量を進めるのが安心です。
購入手続きのステップと必要書類
購入の基本ステップは、売主との売買契約締結、地主承諾取得、登記手続きです。まず売主と価格交渉・重要事項説明を終えた上で売買契約書を作成します(仲介業者経由が一般的)。契約時に買主は手付金を支払い、ローン特約・調査特約を付けるのが一般的です。地主への承諾申請書と必要書類を準備し、承諾料の支払い交渉を行います。承諾を得られたら地主と承諾証を交わして契約完了です。登記に必要なのは、売主から引き継ぐ「登記識別情報(または登記済証)」「印鑑証明書」、買主側では「住民票」「印鑑証明書」、双方の身分証明書や承諾証、売買契約書などです。契約後は、所定期限までに司法書士に登記依頼して名義書換を行います。
融資を引く際の注意点
借地権物件に住宅ローンを利用する際は、貸出金融機関によっては借地権が融資対象外となる場合があります。借地権の評価は土地部分が評価されないため担保価値が低く判断されがちで、借地権付き建物ローンの金利は所有権物件より高く設定されることが多いです。また、借地権契約書の提出や地主承諾書の提出を求められることもあります。融資審査を通すには、担当者に物件の収益性や契約内容を丁寧に説明し、必要なら頭金を増やすなど借入条件を工夫しましょう。借地権ローンに強い金融機関(地元信用金庫や不動産担保ローン専門会社)を探すのも一法です。
トラブル事例と裁判例
地代改定請求を巡るトラブル
地代の増減請求では、借地借家法が優先されることを裁判所が明確にしています。例えば、最高裁は「地代を物価指数が下がっても減額しない」という特約について、借地借家法11条が強行規定であるとして無効と判断しました。すなわち、地代改定権は契約の有無にかかわらず行使可能であり、契約で地代改定を放棄していても法律上の減額請求権を消すことはできません。このため更新時の地代見直しでは、借地人も地主も現状の地代水準が適正かどうか慎重に検討する必要があります。地代改定請求の仲裁や訴訟では、改定請求申立書の作成や裁判所への供託手続きが必要になるケースがあります。
更新拒絶・契約解除の裁判例
借地契約の更新拒絶(立退き請求)には正当事由が必要です。裁判例では、地主が契約満了後に「遅滞なく異議」を述べていない場合は契約が自動更新されたと判断され、地主の請求が認められません。一方、地主が要件を満たし、合法的な立退き事由(建替え計画など)を示した場合は更新拒絶が認められます。判例を知ると、「借地人の賃料不払いや建物老朽化の危険」など、正当事由として認められた事例とそうでない事例があります。契約解除を主張する際は、正当事由の有無の立証が鍵となるため、法的助言を受けて慎重に進めるべきでしょう。
最近の法改正動向と実務への影響
近年は「借地借家法」そのものの大改正はありませんが、2020年に建物譲渡特約付借地権が追加されるなど借地制度の選択肢が増えました。また、2022年の法改正で印紙税の電子化・押印不要化が進み、書面契約の簡便化が図られました。実務的には、地主への承諾料規定や更新料条項の透明化が進む一方で、金融市場の目線から借地権の担保評価が厳しくなっています。借地権契約を巡る紛争では常に最新の判例・条文解釈が問われるため、契約書作成や更新交渉時には弁護士や司法書士への相談が推奨されます。
ユーザーの疑問にお答え!借地権Q&A集
「借地権とは 意味」をもっと詳しく教えて!
借地権は他人の土地を借りて建物を所有する権利で、法律上は地上権や賃借権にあたります。土地所有者(地主)に地代を支払う点で使用貸借とは異なり、契約期間が長期(20~30年以上)で設定され更新権も認められるのが特徴です。建物は借地人の所有物として扱われ、都市計画税などの土地税がかからないメリットがあります。日常語では「借地」「定期借地」「普通借地」など契約形態によって呼び分けられます。
借地権の法律的ポイント(旧法/新法の違い)は?
旧法(1960年施行の借地法)の借地権は自動更新が原則で借地人保護が強いのに対し、新法(1992年施行の借地借家法)では普通借地権と定期借地権が区分され、更新ルールが明確化されています。旧法契約では更新拒絶に正当事由が必要で更新料も高額になる傾向がありますが、新法契約では期間満了で地主に更地返還できる定期借地権や更新時に更新料を支払う普通借地権など、地主・借地人の双方に配慮した制度が設けられています。
契約期間・更新方法でよくある質問は?
普通借地権の契約期間は初回30年以上、更新も原則できます。更新料の支払いが条件になることが多いです。定期借地権は期間終了時に土地を明け渡す約束です。更新拒絶したい地主は、契約満了時に「遅滞なく異議」を通知しなければ契約が更新されるので注意が必要です。借地人は更新したくない場合、満了1年前から半年ほど前までに更新拒絶の意思表示をする必要があります。
更新料・承諾料の目安は?
更新料は借地契約更新時に地主に支払う金銭で、更地価格の3~5%程度が相場です。譲渡承諾料(名義書換料)は借地権価格の10%前後、建替え承諾料は地価の3~5%程度が一般的な目安です。具体的金額は土地の規模・場所で大きく変わるため、不動産業者や専門家に相場確認を依頼するとよいでしょう。
相続対策でよくある質問は?
借地権も相続財産なので相続税の対象です。相続税評価では路線価の3~9割で計算され、都市部ほど評価割合が高くなります。相続対策としては、借地権割合(借地人の持ち分割合)が高い地域では、土地(底地)の相続分を少なくする遺言や共有対策などが検討されます。また、借地権を生前に底地ごと売却・贈与してしまう手法もありますが、地主の同意や承諾料問題が発生するので専門家に相談しましょう。
費用相場を知りたいです!
月々の地代は土地評価額と利用用途次第ですが、住宅地で月1~5万円台、商業地なら数万円~数十万円と幅広いです。契約更新料・承諾料は数%の範囲で前述の通り。その他、売買や相続時の司法書士報酬(数万円~数十万円)や登記費用(登録免許税0.2~0.4%)も必要になります。確定測量は一般に50~80万円程度かかる点も考慮してください。
売却時の注意点まとめは?
借地権付き建物の売買では、「地主の承諾」が最大の注意点です。承諾が得られないと売買契約が無効になるので、最優先で承諾書を取得します。買主候補には借地契約の内容を十分説明し、地代や期間、更新ルールなどを理解してもらいます。売買契約書には借地権の特約(承諾取得、引渡し日後の建物明渡し条項など)を盛り込みましょう。また、相続発生後に売却する場合も地主への通知を忘れずに。売却益には譲渡所得税がかかるので税務面もチェックが必要です。
トラブルが起きたらどうする?必要書類・対応策は?
地代紛争や更新拒絶トラブルでは、まず借地契約書・承諾書・更新通知書など契約関連書類を整理します。法的対処が必要な場合は、内容証明郵便での意思表示や調停・裁判手続きが考えられます。借地権関連の法令・判例は専門性が高いため、弁護士・司法書士への早めの相談が大切です。公的機関では国土交通省の借地借家法Q&Aや市区町村の相談窓口も活用できます。
まとめ
- 借地権チェックリスト: 借地契約の種類(旧法・新法・定期)、契約期間、地代額・改定条項、更新料・承諾料の有無、地主の連絡先、建替え承諾要件をまず確認しましょう。
- 各種手続きのポイント再整理: 売買時は地主承諾が必須。相続時は建物登記名義変更+地主への通知で対応。契約更新時は更新料の相場を事前把握し、場合によっては交渉で条件を抑える。費用・税金・登記免許税の計算も忘れずに。

住援株式会社 代表取締役社長
辻 祥平 | Tuji Shohei
多くの不動産業者が「顧客を騙して稼ぐ」ことが一般的な中、自分の周りの大切な人々に良い不動産を提供したいという想いで創業。「不動産業界の真実を本音で伝える営業スタイル」「綿密な収集シミュレーションの提供」「お客様が真に納得するまで取引を進めないという信念」に基づき行う提案からお客様からの絶大な信頼を得る。実績:賃貸・売買 総合売上高1位 / 執行役員 (前職不動産会社)